洗濯にお風呂の残り湯を使えば、水道代が節約できると考えている方は多いのではないでしょうか。
しかし最近では、「残り湯洗濯は節約にならない」といった声も聞かれるようになりました。その背景には、電気代の増加や手間、衛生面の問題など、さまざまなデメリットが存在しています。
たとえば、残り湯を汲み上げるためのポンプや洗濯機自体の消費電力によって、節約したはずの水道代が電気代で相殺されてしまうこともあります。
また、「風呂の残り湯洗濯をやめた」という人の中には、入浴剤の成分による衣類の傷みや、翌日に使うことで発生する雑菌や臭いの問題に悩まされたという声もあります。
実際、残り湯で洗濯するとどれくらい節約できますか?あるいは、風呂の残り水で洗濯をするとどれくらい節水できますか?と疑問を抱く方もいらっしゃるかと思います。
たしかに、毎日使用すれば年間で数千円分の節水が可能です。しかし、その一方で「残り湯洗濯はよくない」と感じる要因が存在しているのも事実です。
また、最近では水の使用量を抑えたドラム式洗濯機が普及し、そもそも残り湯を使う必要性が低くなってきています。こうした環境の変化も、「残り湯洗濯は節約にならない」と言われる理由の一つです。
この記事では、残り湯洗濯が本当に節約につながるのかを検証しながら、電気代や水道代の実態、使い続ける上でのデメリットなどをわかりやすく解説していきます。ご家庭にとって最適な洗濯方法を見つけるための参考にしていただければ幸いです。
- 残り湯洗濯が節約にならない理由とコストの内訳
- 電気代や手間などによる意外なデメリット
- 水道代やドラム式洗濯機との比較による節約効果の違い
- 入浴剤や翌日使用時の衛生リスク
残り湯洗濯が節約にならない理由とは?
- 節約にならない電気代の実態
- 風呂の残り湯洗濯をやめた理由に多い声
- 水道代の変化とは
- ドラム式との比較
- デメリットを整理して解説
節約にならない電気代の実態

残り湯を使った洗濯は水道代の節約につながると思われがちですが、実は電気代の増加によって節約効果が薄れるケースがあります。とくに見落とされやすいのが、給水ポンプや洗濯機本体による電力消費です。
なぜ電気代が問題になるかというと、残り湯を汲み上げるためにはバスポンプなどの電動機器が必要であり、その稼働に電力を使うからです。たとえば、一般的なポンプの消費電力は20W程度で、一度の洗濯で10分間使用すると、約0.1円の電気代がかかります。これは一見微々たる金額のように思えるかもしれません。
しかし、洗濯機自体の消費電力も含めて計算すると、1回の洗濯で合計約7~8円の電気代がかかるとされています。これを月30回行えば、月間で200円以上の電気代がかかることになります。つまり、水道代の削減分と相殺されてしまい、実質的な節約にはならない可能性があるのです。
また、夜間や早朝に洗濯を行うことで電気料金が安くなるプランを活用する手もありますが、そのためには時間帯の管理や騒音への配慮も必要です。こうした点から、残り湯洗濯は単純な節約手段とは言いきれず、電気代を含めたトータルコストの見直しが求められます。
風呂の残り湯洗濯をやめた理由に多い声
風呂の残り湯を使った洗濯は一見節約になりそうですが、実際にはやめたという人の声も少なくありません。その背景には、日々の生活の中で感じる不便さや衛生面の不安があるようです。
最もよく聞かれる理由は、「雑菌や臭いが気になる」というものです。入浴後の残り湯には皮脂や石けんカスが含まれており、放置しておくと雑菌が増えやすくなります。とくに、夏場など気温の高い時期には水が傷みやすく、洗濯物に嫌な臭いがついてしまうケースもあります。
次に挙げられるのは「手間がかかる」という声です。残り湯を使うにはバスポンプやホースの設置・掃除が必要で、使い終わった後もメンテナンスが欠かせません。ホースの内部に汚れが溜まると、逆に洗濯物を汚すリスクもあります。忙しい家庭にとって、この一手間が大きなストレスになるのです。
さらに、「給水ポンプの音がうるさい」「洗濯機の操作が面倒」など、設備面での不満も聞かれます。特に夜間に洗濯する場合、動作音が近所迷惑にならないか気を使う必要があることも、やめる要因の一つです。
このように、残り湯洗濯は一部では節約として効果を発揮する反面、実際には継続することが難しいと感じる人が多い方法でもあります。家庭のライフスタイルや衛生意識によっては、無理に続けるよりも別の節約方法を選ぶほうが現実的かもしれません。
水道代の変化とは
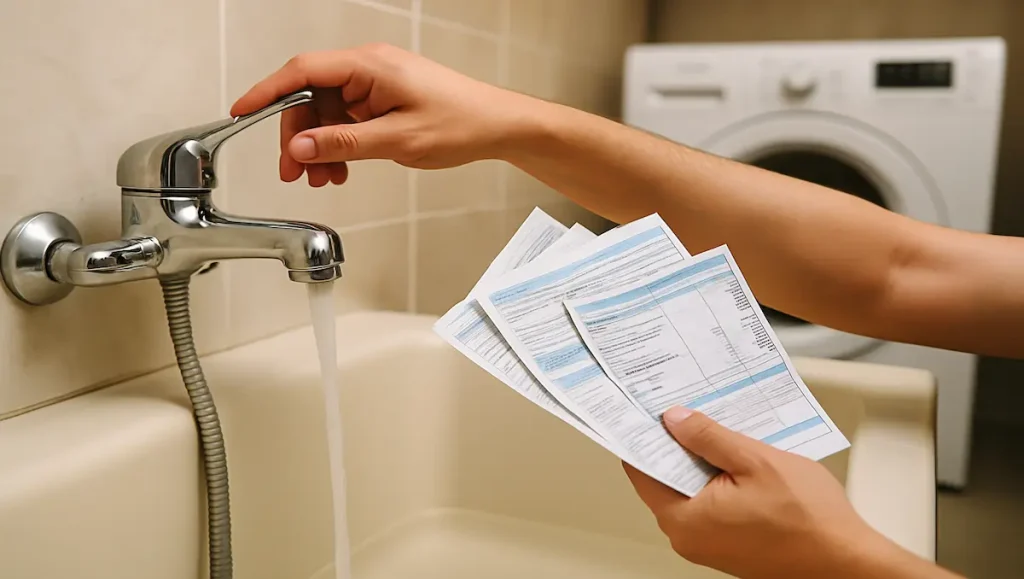
残り湯を使った洗濯をやめると、水道代が増えるのではないかと心配される方が多いかもしれません。ですが、実際には家庭の洗濯スタイルによって水道代の変化はそれほど大きくない場合もあります。
なぜかというと、残り湯が使えるのは洗いの工程のみで、すすぎには水道水を使うのが一般的だからです。つまり、もともと洗濯全体の水の一部しか節約できていなかったケースが多いのです。
例えば、1回の洗濯で100リットルの水を使用するうち、洗いに使う50リットルだけを残り湯にしていたとします。仮に1リットルあたり0.24円の水道代で換算すると、1回あたり約12円の節約になります。これを月に30回行っていたとしても、360円程度の差しか生じません。
また、残り湯洗濯をやめることで得られるメリットもあります。例えば、ポンプの掃除やセットの手間がなくなる点や、衛生面の不安を気にしなくてよくなる点です。こうした精神的・物理的な負担の軽減を水道代とのバランスで考えることも大切です。
このように、残り湯洗濯をやめた場合の水道代の増加は意外と小さく、その代わりに得られる手間の軽減や安心感を重視する人も多くいます。
ドラム式との比較
ドラム式洗濯機を使っている家庭では、そもそも残り湯洗濯の必要性が低くなる傾向にあります。なぜなら、ドラム式は縦型洗濯機に比べて使用する水の量が少なく、水道代が抑えられる設計になっているためです。
ドラム式の洗濯機は、1回の洗濯で約50リットル前後の水しか使わないモデルも多く、これは縦型の約半分です。このため、残り湯を使わずとも水道代が節約できるという特長があります。
また、残り湯をドラム式に使うには対応機種や専用ポンプが必要なケースがあり、導入のハードルがやや高くなります。そのうえ、ドラム式は「すすぎ1回」などの省水設定にも対応しているため、そもそも追加の工夫なしで節水効果が期待できます。
一方で、初期投資としてドラム式洗濯機は価格が高い傾向にありますが、長期的に見れば水道代や電気代の削減効果で元が取れるという考え方もできます。
このように比較すると、ドラム式を使用している家庭では、残り湯洗濯をやめても水道代の増加はほとんどなく、むしろ効率的な洗濯が可能になるケースも多いのです。洗濯機の種類に応じた節約方法を選ぶことが、無理のない節約につながります。
デメリットを整理して解説

残り湯を使った洗濯には一定の節約効果がある一方で、注意すべきデメリットもいくつか存在します。これらをあらかじめ把握しておくことで、後悔のない選択ができるようになります。
まず最も多く挙げられるのが、衛生面の不安です。お風呂の残り湯には、皮脂汚れや石けんカスが含まれており、時間が経過すると雑菌が増殖しやすくなります。こうした水を使って洗濯をすると、衣類に臭いが残ったり、生乾き臭の原因になったりすることがあります。
次に、衣類への影響も無視できません。残り湯の温度や入浴剤の成分によっては、生地が傷んだり色移りしたりする可能性があります。とくにデリケートな衣類や濃い色の衣類には注意が必要です。
さらに、使い勝手の面でも課題があります。給水ポンプの設置や管理が必要になるほか、使用後の掃除を怠るとホース内にカビが発生する恐れもあります。このような手間をわずらわしく感じる人も少なくありません。
このように、節約だけを重視して残り湯洗濯を取り入れると、思わぬ手間や不快感に悩まされることがあります。効果と負担のバランスを見極めることが重要です。
残り湯洗濯が節約にならない場合の対策
- 残り湯で洗濯するとどれくらい節約できますか?
- どれくらい節水できますか?
- 残り湯の翌日使用は避けるべき?
- 残り湯洗濯がよくないと言われる原因
- 入浴剤使用時の注意点
残り湯で洗濯するとどれくらい節約できますか?

残り湯を洗濯に使うと、水道代の削減につながりますが、その節約額はどのくらいか気になる方も多いでしょう。日常的に洗濯をしている家庭であれば、年間で数千円単位の節約が期待できます。
具体的に見ていきましょう。洗濯1回で使用する水のうち、洗い工程に使う約50リットルを残り湯に置き換えると、1リットルあたり0.24円の水道代を基準にして、1回あたり約12円の節約になります。
これを月に25回洗濯した場合、月間で約300円、年間でおよそ3,600円の水道代が浮く計算です。頻度が高ければそれだけ効果も大きくなり、例えば1日2回洗濯する家庭では、年間6,000円以上の節約になることもあります。
ただし、ポンプの電気代や洗剤の追加使用など、わずかですがコストが発生する点も無視できません。こうした追加費用を差し引いても、水道代の削減効果は明確に感じられるため、無理なく続けられる家庭にはおすすめできる方法です。
どれくらい節水できますか?
風呂の残り水を使って洗濯を行うと、どれほどの節水になるのかを具体的な数値で見ていきましょう。洗濯の際に使う水量は、家庭用洗濯機でおおよそ100リットル程度。そのうち、洗いに使う水を残り湯でまかなう場合、約50リットル分の節水となります。
これを月単位で換算すると、50リットル × 30日 = 1,500リットル。年間では18,000リットルもの水道水の使用を抑えられることになります。これは家庭用のお風呂約90杯分に相当する量です。
また、これだけの水を使わずに済むということは、水資源の保護にもつながります。節水を意識する人にとって、環境負荷の低減にも貢献できる方法といえるでしょう。
なお、洗濯の全工程を残り湯で行うことは難しく、すすぎには水道水が必要です。そのため完全な節水とはなりませんが、洗い工程だけでも十分な効果がある点は見逃せません。
日々の積み重ねによる節水効果は思った以上に大きく、家計にも環境にも優しい選択肢の一つと言えるでしょう。
残り湯の翌日使用は避けるべき?

残り湯を翌日に持ち越して洗濯に使うことは、衛生面の観点からあまりおすすめできません。時間が経過した残り湯は、雑菌が繁殖しやすい状態になるためです。
特に気温が高い夏場や湿度の高い日には、お風呂のお湯に含まれる皮脂や石けんカスを栄養にして、雑菌が一気に増えやすくなります。ある調査では、入浴直後と比べて翌朝には雑菌数が1000倍以上に増加するというデータもあります。
たとえ見た目がきれいでも、時間が経った残り湯はすでに衛生的とは言いにくく、洗濯物に生乾き臭がつく原因にもなります。また、菌が繊維に残ることで、肌の弱い人には刺激になる可能性もあるため注意が必要です。
どうしても翌朝に使用したい場合は、風呂のふたを閉めてホコリの侵入を防ぎ、使用前に抗菌剤や酸素系漂白剤を併用することである程度の対策は可能です。しかし、最も安心できるのは「入浴後すぐに使用すること」だといえるでしょう。
残り湯洗濯がよくないと言われる原因
残り湯を洗濯に使うことは節約になる一方で、「やめたほうがいい」と言われる理由も確かに存在します。これらの原因を理解することで、より適切な選択ができるようになります。
まず一番多いのが、衛生面への不安です。お風呂の残り湯には入浴中に落ちた皮脂や髪の毛、石けんカスなどが含まれており、時間が経つと雑菌が繁殖しやすくなります。こうした水を使うと、洗濯物に臭いが移ったり、洗濯槽にカビが発生する可能性もあります。
また、手間の多さも見逃せない要因です。残り湯を使うには給水ポンプやホースの設置が必要で、使用後のメンテナンスも欠かせません。忙しい毎日の中でこの作業を続けるのは負担になることがあります。
加えて、入浴剤を使用している場合も注意が必要です。一部の入浴剤は色素や成分が強く、衣類に色移りや傷みを引き起こす可能性があります。パッケージに「洗濯使用不可」と書かれている場合は、洗濯に使わないようにしましょう。
このような点から、「残り湯洗濯はよくない」と言われることがあるのです。実施する際は、手間とリスクをきちんと理解し、状況に応じて無理なく取り入れることが大切です。
入浴剤使用時の注意点

入浴剤を使ったお風呂の残り湯を洗濯に利用する場合には、いくつかの点に注意が必要です。見落としがちなポイントですが、正しく対処しなければ衣類の色移りや洗濯機の故障を招くこともあります。
まず確認すべきは、入浴剤のパッケージに記載されている「洗濯使用可否」です。すべての入浴剤が洗濯に適しているわけではありません。「残り湯は洗濯に使えません」と明記されている場合、その成分が衣類に付着し、色移りや素材の劣化を引き起こす可能性があります。
また、着色料や香料、オイル系成分が多く含まれる入浴剤には特に注意が必要です。こうした成分は衣類だけでなく、洗濯槽の内側にも残留しやすく、ぬめりやカビの原因になることがあります。定期的な洗濯槽クリーナーの使用で対応はできますが、予防の意味でも入浴剤の選定は慎重に行いましょう。
どうしても入浴剤入りの残り湯を使いたい場合は、色物の衣類やデリケートな素材を避け、タオルや作業着など、多少の変化が許容できるものに限定して使うという選択肢もあります。
このように、入浴剤の有無や種類によって洗濯への影響は大きく異なります。使用前に成分や注意書きを確認し、安全に残り湯を活用することが大切です。
残り湯洗濯が節約にならない理由を総まとめ
この記事のポイントをまとめます。
- ポンプや洗濯機の電気代が水道代の節約分を打ち消す
- バスポンプ使用時の電力消費が毎月積み重なる
- 夜間洗濯は電気代が安くなるが騒音トラブルのリスクがある
- 衛生面の不安から洗濯物に臭いが残ることがある
- 夏場は雑菌が増えやすく洗濯に不向きな状態になりやすい
- ポンプやホースの設置・掃除の手間がかかる
- ホース内の汚れが洗濯物を汚す可能性がある
- 給水ポンプの音がうるさくストレスになる
- 操作の複雑さや手間で継続が難しくなることが多い
- すすぎには水道水が必要なため完全な節水にならない
- 実際の水道代の差額は月数百円程度と小さい
- ドラム式洗濯機は水量が少なく残り湯不要でも節水可能
- 入浴剤入りの残り湯は衣類の色移りや傷みの原因になる
- 翌日の残り湯は雑菌が多く衛生的でない
- 洗濯槽のカビやぬめりの原因になることがある
くらしのマネハックの評価は…
| 項 目 | 評 価 |
|---|---|
| 効 果 | |
| 再現性 | |
| 難易度 |
総合評価:Cランク
(使う前に注意点をしっかり確認)
 まねは
まねは無理に取り入れるよりも、洗濯機の見直しや夜間プランなど他の節約手段を検討してみてください。
残り湯を使った洗濯は一見お得に感じられるかもしれませんが、実際には電気代や手間、衛生面などさまざまなハードルがあります。
節水効果がある一方で、それを上回る負担を感じる方も少なくありません。もし少しでも「面倒だな」と感じたら、ドラム式洗濯機やタイムプランの見直しなど、他の選択肢にも目を向けてみることをおすすめします。








