浄化槽のブロワーは24時間365日稼働しているため、気がつかないうちに電気代の負担が積み重なっていることがあります。特に冬の電気代が気になる時期や、アパート浄化槽のように複数世帯分をまとめて管理している場合には、その影響はより大きくなります。
本記事では、浄化槽の電気代節約をテーマに、ブロワーの消費電力を抑える方法や、安永製ブロワーなど省エネ性に優れたおすすめ機種の紹介を行います。また、電気容量の確認方法や、家庭用電源で安全に使用するための注意点についても触れています。
さらに、「電源をオフにしたらどうなる?」といった疑問や、「浄化槽の電気を止めるのは安全か」といった不安をお持ちの方にも向けて、専門的な視点からリスクと対策を丁寧に解説しています。
加えて、ブロワーと水槽ブロアーの消費電力を比較しながら、省電力設計の特性についても分かりやすくご紹介します。「浄化槽のブロワーは省電力ですか?」という疑問をお持ちの方も、きっと参考になるはずです。
日常的な節約はもちろん、長期的な維持費を抑えたい方にも役立つ情報をまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。
- 浄化槽ブロワーの消費電力と電気代の目安
- 電気代を抑えるための具体的な節電方法
- ブロワーの選び方と省エネモデルの特徴
- 電源を切るリスクと安全な節電対策
浄化槽の電気代節約|基本を解説
- 消費電力目安と計算方法
- 浄化槽の電気容量をチェックしよう
- 安永製ブロワーの電気代はどれくらい?
- 浄化槽のブロワーは省電力ですか?
- 水槽用ブロアーの電気代と比較してみた
消費電力目安と計算方法

浄化槽に使われるブロワーの消費電力は、製品の風量や型式によって異なりますが、一般的には30W〜80W程度が目安です。この消費電力が、日々の電気代にどの程度影響するかを知ることで、ムダな支出を抑えることができます。
目安として、50Wのブロワーを24時間稼働させた場合、1日の電力消費量は約1.2kWhです。これを電気料金の平均単価(27円/kWh)で計算すると、1日あたり32.4円となり、月に換算すると約972円、年間で約11,664円になります。
例えば、省エネ型のブロワーで消費電力が30Wに抑えられている機種を使用した場合、同じ計算式で1日0.72kWh、月額約583円と、年間では約7,000円台に収まります。このように、たった数十ワットの違いでも、長期的には数千円単位の差が出てくるのです。
また、電気代を正確に知りたい場合は、実際のブロワーの消費電力(W)と1日の稼働時間、電力会社の単価(円/kWh)を掛け合わせると、詳細なコストを把握できます。
ブロワーは基本的に24時間稼働するため、選定時には消費電力の小さな製品を選ぶことが節電につながります。導入前に必ずスペック表を確認し、電気代のシミュレーションを行うことをおすすめします。
浄化槽の電気容量をチェックしよう
浄化槽に使用されるブロワーや関連機器の電気容量を確認することは、安全に使用するために欠かせません。特に、電気回路に複数の家電が接続されている場合は、ブレーカーの容量オーバーを防ぐためにも重要です。
ここで言う「電気容量」とは、家庭内のブレーカーやコンセントが許容する電力の上限のことを指します。一般的な家庭用コンセントの容量は15Aで、100V換算だと最大1,500Wまで使用可能です。浄化槽のブロワー単体では数十ワットと比較的少ないものの、他の機器と併用している場合は注意が必要です。
例えば、46Wのブロワーを常時稼働させていても、同じ回路に冷蔵庫(100W前後)や照明、電子レンジなどが繋がっていれば、瞬間的に容量を超えるリスクがあります。これが原因でブレーカーが落ちると、浄化槽の機能も一時的に停止する恐れがあります。
このような事態を避けるためには、使用しているブロワーの消費電力を確認し、どの回路に接続されているかを把握することが第一です。特に古い住宅では、電気容量が低いケースもあるため、分電盤や契約アンペア数の確認も行いましょう。
いずれにしても、ブロワーを安全かつ効率よく運用するには、家庭の電気設備とのバランスを考慮する必要があります。設置前や買い替え時には、専門業者に相談するのも一つの手です。
安永製ブロワーの電気代はどれくらい?

安永製のブロワーは省エネ性能に優れており、月あたりの電気代はおおよそ600円〜1,200円程度が一般的です。使用している機種や風量によって消費電力が異なるため、電気代にも差が出ます。
例えば、風量が40L/minの小型タイプで消費電力が約30Wのモデルであれば、1日24時間稼働した場合の電気代は月に約600円前後になります。一方、80L/minクラスの機種では消費電力が60Wを超えるものもあり、同じ稼働時間で月額1,200円程度まで上がることがあります。
ここで気をつけたいのが、フィルターの劣化や内部パーツの摩耗です。これらが進行すると消費電力が増加し、想定より電気代がかかるケースもあるため、定期的なメンテナンスは欠かせません。
また、電力単価は地域や契約プランによって異なるため、実際の電気代は多少前後します。正確な金額を知るには、使用しているブロワーのW数と、契約中の電力単価を使って計算するのが確実です。
安永のブロワーは静音性と耐久性も評価が高く、長期的なコストを抑えたい方に向いています。購入時にはスペックを確認し、必要以上の風量を持つモデルを選ばないよう注意しましょう。
浄化槽のブロワーは省電力ですか?
多くの家庭用浄化槽ブロワーは、比較的省電力で設計されています。特に最近のモデルではエネルギー効率が向上しており、電気代の負担を抑えながら安定した運転が可能です。
1日に消費する電力量は、一般的な50Wのブロワーであれば約1.2kWh。1kWhあたりの電気料金を27円とすると、1日で32.4円、月間では約972円という計算になります。これは、冷蔵庫などの家電と比べても、決して高い数値ではありません。
ただし、すべてのブロワーが省電力というわけではありません。旧型のブロワーや風量が過剰なタイプを使用している場合、必要以上に電気を消費している可能性があります。特に10年以上前のモデルは、最新機種と比較して2倍近くの消費電力がある場合も珍しくありません。
また、フィルターの詰まりや部品の劣化によってブロワーに負荷がかかり、省エネ性能が発揮されにくくなることもあります。このような状態では、見かけ上は省電力でも実際の消費電力が増えてしまうことがあるため注意が必要です。
このように考えると、浄化槽のブロワーは本来省電力な機器ですが、使用状況やメンテナンスの有無によって電気代に大きな差が生まれます。定期点検と適切なモデル選びが、節約のカギとなります。
水槽用ブロアーの電気代と比較してみた

浄化槽に使われるブロワーと水槽用のブロアーでは、消費電力や稼働条件が異なります。そのため、電気代にも明確な差が出ることがあります。
一般的な水槽用ブロアーは、10W〜20W程度の小型機種が多く、主に観賞魚用のエアレーションやろ過装置に使われます。24時間稼働させたとしても、1日あたりの電気代は5〜10円程度に収まることがほとんどです。月額で見ると、電気代は300円以下というケースも珍しくありません。
一方で、浄化槽用のブロワーは風量が大きく、30W〜80W程度の消費電力が一般的です。家庭の排水処理を維持するために連続稼働が求められるため、月間の電気代は1,000円前後、場合によってはそれ以上になります。
つまり、水槽用のブロアーに比べて浄化槽用ブロワーの方が消費電力は高く、それに伴って電気代もかかります。ただし、それは必要な空気量や稼働時間が異なるためであり、単純に効率が悪いわけではありません。
このように、どちらのブロワーも用途に応じた適正な仕様になっており、電気代の差は「目的と規模の違い」によるものです。節電を考える際は、必要な機能を維持しつつ無駄を省く視点が大切です。
浄化槽の電気代節約|実践アイデア
- 浄化槽の電気を止めるのは安全?
- 電源をオフにしたらどうなる?
- 冬にかかるコストとは
- アパートの浄化槽|電気代の抑え方
- おすすめ省エネブロワー
- 電気代を抑えるタイマー活用法
浄化槽の電気を止めるのは安全?

ブロワーの電源を意図的に止めることは、浄化槽の機能に大きな影響を与える可能性があります。特に長時間にわたって電源を切るのは、安全とは言い切れません。
浄化槽のブロワーは、槽内に空気を送り込み微生物の活動を維持するために常時稼働しています。この空気供給が止まると、好気性微生物が酸欠状態に陥り、排水の分解が不十分になったり、悪臭の原因になったりすることがあります。
一時的な停電や短時間の電源OFFであれば大きな問題に至ることは少ないですが、数時間以上の停止や、毎日のように間欠的に止める設定をすると、処理能力に影響を及ぼすことがあります。また、合併浄化槽では夜間に「逆洗」という重要な工程が行われるため、このタイミングで電源を切ると処理バランスが崩れる可能性もあります。
タイマーなどで稼働時間を短縮する方法もありますが、導入にあたっては専門業者や浄化槽管理士のアドバイスを受けることが推奨されます。安易に電源を切ると、法定水質基準を満たさなくなることもあるため注意が必要です。
このように、浄化槽の電源を止める行為にはリスクが伴います。節電を検討する際は、ブロワーの買い替えや省エネ型への変更など、機能を損なわない方法から優先して検討すると良いでしょう。
電源をオフにしたらどうなる?
浄化槽の電源、特にブロワーの電源をオフにすると、浄化機能そのものに大きな支障が出る可能性があります。ブロワーは槽内に酸素を送り、汚水を処理する微生物の活動を支える役割を担っているため、電源が停止すればその働きが弱まります。
酸素の供給が止まると、好気性微生物が酸欠状態になり、排水の分解が進まなくなります。結果として、浄化不良や悪臭の発生、水質の悪化といった問題が起こるおそれがあります。また、長期間電源を切ってしまうと、微生物の死滅によって浄化槽内のバランスが完全に崩れてしまうこともあります。
一方で、短時間の電源オフ(数時間以内)であれば、大きな影響が出ないこともあります。ただし、日常的に電源を切ったり間欠運転を繰り返したりするのは、トラブルの原因になりかねません。特に合併処理浄化槽では、夜間に逆洗や曝気の工程が自動で行われるため、深夜帯の停止は避けるべきです。
このように、浄化槽の電源をオフにすることにはリスクがあり、節電目的であっても慎重な判断が必要です。対策としては、省エネ型ブロワーへの買い替えや、専門業者による稼働時間の最適化を検討するのが現実的です。
冬にかかるコストとは
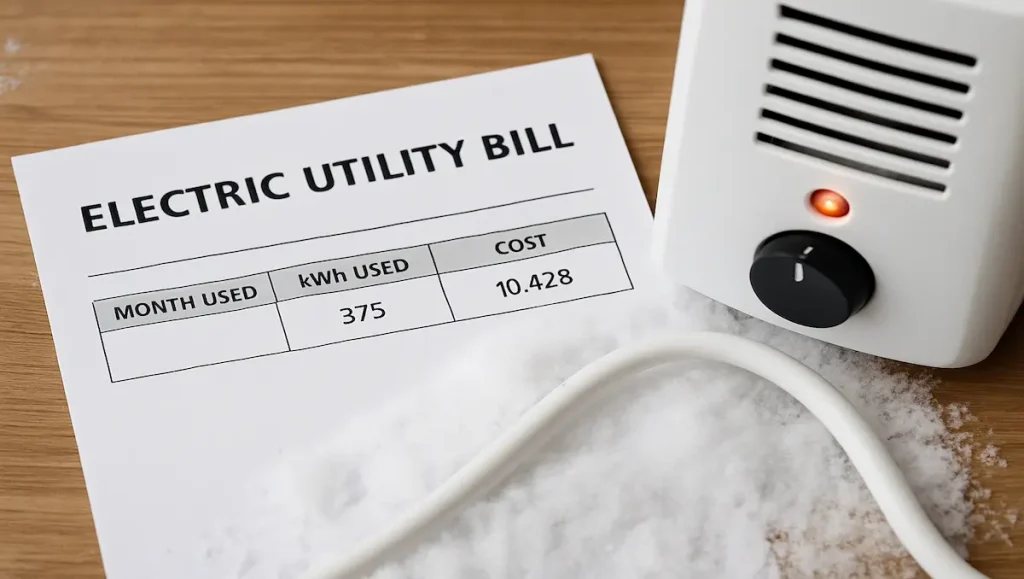
冬場の浄化槽の電気代は、他の季節と比べて大きな変動は少ないものの、家庭内の電力消費が増える時期であるため、全体の負担感が増す傾向にあります。浄化槽のブロワーは季節を問わず24時間稼働するため、使用電力量自体は年間を通じてほぼ一定です。
たとえば、50Wのブロワーを使っている場合、1日あたりの電気代は約32円。1か月でおよそ1,000円前後となります。これが冬でも基本的には変わりませんが、暖房器具や照明の使用時間が長くなるため、電気代全体が高く感じやすくなるのです。
また、寒冷地では気温の低下によってブロワーの負荷が増すこともあり、微細ながら消費電力が上昇するケースもあります。特に古い機種や、経年劣化しているブロワーでは、稼働効率が落ちて電気を多く消費することも考えられます。
このとき、家庭全体の電気代を抑えるためには、浄化槽ブロワーの見直しも一つの方法です。省エネ型のブロワーに切り替えることで、年間のコストを2,000円〜4,000円程度削減できるケースもあります。
冬にかかる電気代を把握するには、HEMS(家庭のエネルギー管理システム)などを使ってブロワーの使用状況を見える化するのも効果的です。正確な把握ができれば、無駄な電力消費を防ぐきっかけになります。
アパートの浄化槽|電気代の抑え方
アパートなどの集合住宅では、複数世帯分の排水処理を行うため、浄化槽のブロワーも大型のものが使われます。その分、電気代も高くなりやすく、年間で数万円規模のコストが発生することもあります。ここでは、そうした電気代を抑える方法を紹介します。
まず効果的なのは、省エネ型のブロワーへ交換することです。従来型に比べて消費電力が20〜30%下がる製品もあり、月に1,000円以上節約できる場合もあります。特に「ダイヤフラム式」で定格消費電力が50W未満の機種はコストパフォーマンスが高く、人気があります。
次に、稼働の見直しも検討材料になります。ただし、浄化槽の連続運転が基本となるため、勝手に運転時間を短縮するのは避けるべきです。設置状況や使用人数を踏まえ、管理業者と相談しながら間欠運転を取り入れるなど、安全な方法で調整する必要があります。
さらに、メンテナンスも重要なポイントです。フィルターの詰まりや部品の劣化があると、ブロワーに余計な負荷がかかり、電気代が無駄に増えてしまいます。定期点検と清掃を行うことで、本来の省エネ性能を維持できます。
これらの方法をバランスよく取り入れることで、アパートの浄化槽にかかる電気代を効率よく削減することが可能になります。
おすすめ省エネブロワー

省エネ性能に優れた浄化槽ブロワーを選ぶことで、年間の電気代を大きく抑えることが可能です。現在販売されているブロワーには、従来型に比べて消費電力が低く、静音性や耐久性にも優れた製品が多数あります。
まずおすすめしたいのは、フジクリーンの「EcoMACシリーズ」です。たとえばEcoMAC60は風量60L/minに対して消費電力が約33Wと非常に低く、電気代を抑えながら安定した空気供給が可能です。騒音レベルも控えめで、住宅地でも使いやすいモデルです。
もう一つの人気機種が、テクノ高槻の「XP-40」です。こちらは40L/min対応で消費電力が24W~30Wと省エネ性能が高く、小規模家庭や5~6人槽に適しています。小型ながら耐久性があり、フィルターも長持ちしやすい点が魅力です。
さらに、ダイヤフラム式で定評のある安永エアポンプのAPシリーズも選択肢に入ります。たとえばAP-60Fは風量60L/minで消費電力が約38W程度。パーツ交換がしやすく、長期運用にも対応しやすいモデルです。
いずれの製品も、ブロワーの基本性能である「風量」と、設置する浄化槽の人槽(使用人数目安)に合っているかを確認することが重要です。過剰な風量は無駄な電気消費につながり、逆に風量が足りなければ処理不良を招く可能性があります。
このように、省エネブロワーを選ぶ際は、消費電力の低さだけでなく、風量の適正・静音性・耐久性など複数の要素を総合的に比較することが大切です。長期的なランニングコストの削減につながるかどうかを意識して選定するとよいでしょう。
電気代を抑えるタイマー活用法
浄化槽のブロワーにタイマーを取り付けることで、稼働時間を調整し、電気代の削減につなげる方法があります。ただし、浄化槽の機能を維持するうえで注意すべき点もあるため、正しい知識が必要です。
タイマーを使うメリットは、ブロワーの稼働を一定の時間帯に限定できる点にあります。例えば、家族の生活リズムに合わせて日中だけ運転し、使用しない深夜や外出時間帯は停止させるよう設定すれば、1日の稼働時間を半分以下に減らすことも可能です。
このようにすれば、消費電力が50Wのブロワーでも、24時間稼働で月1,000円近くかかっていた電気代が、12時間稼働で約500円まで下げられます。1年間では6,000円前後の差になります。
ただし、ブロワーの間欠運転は浄化槽の種類や使用状況によって向き・不向きがあります。特に合併処理浄化槽では、夜間に「逆洗」や「ばっ気」などの処理工程が行われている場合があり、無闇に止めると処理性能が落ちるリスクがあります。
そのため、タイマー活用前には、保守点検業者や浄化槽管理士に相談し、自宅の浄化槽に適した設定時間やタイミングを把握しておくことが大切です。また、使用するタイマーは屋外対応・防雨型のものを選び、安全な設置環境を整えるようにしましょう。
このように、適切なタイマー運用は電気代の節約につながりますが、浄化機能を損なわない工夫が必要です。節電と性能維持のバランスを取りながら、効率的に活用しましょう。
浄化槽の電気代節約のために知っておきたい要点まとめ
この記事のポイントをまとめます。
- ブロワーの消費電力は30W〜80Wが一般的
- 50Wブロワーは月約1,000円、年約12,000円の電気代がかかる
- 消費電力30Wの省エネ機種なら月600円程度に抑えられる
- 実際の電気代は電力単価と稼働時間で決まる
- ブロワーは基本的に24時間稼働を前提としている
- 電気容量オーバーを避けるため回路の負荷状況を確認する
- ブロワーは省電力設計でもメンテナンス不足で効率が落ちる
- 古いモデルは最新機種に比べて電力消費が2倍近くになることもある
- 安永製ブロワーは静音性と省エネ性に優れている
- 水槽用ブロアーは浄化槽用より消費電力が少ない
- 浄化槽ブロワーの電源は基本的に切らない方がよい
- 合併処理浄化槽は夜間に処理工程があり間欠停止に注意が必要
- 冬場は消費電力は変わらないが全体の電気代負担が増す傾向
- アパートでは省エネブロワー導入とメンテナンスが節電に効果的
- タイマー活用は管理士の指導を受けたうえで導入すべき
くらしのマネハックの評価は…
| 項 目 | 評 価 |
|---|---|
| 効 果 | |
| 再現性 | |
| 難易度 |
総合評価:Aランク
(安心して、しっかり節約できる)
 まねは
まねは節電は“切る”より“替える”が基本!省エネブロワー+メンテナンスで安心節約◎








